中小企業診断士一次試験|【企業経営理論】“ラッキー枠”で受けたら本当に受かった話
こんにちは。中小企業診断士を目指して勉強中のmasaniiです。
今回は、一次試験科目の中でもボリュームが多く、難関とされる「企業経営理論」について、私がどのように取り組み、結果的に合格できたかをまとめてみました。
正直なところ、この科目は「今年は受けなくてもいいかな」と思っていたものの、“もし受かればラッキー”枠として挑戦し、結果的に合格。そんな偶然にも見える合格までの流れには、自分なりの戦略や判断がありました。お役に立てる内容もあると思うので、ぜひ参考にしてみてください。
2024年9月、まずは企業経営理論からスタート
中小企業診断士の勉強を始めたのは2024年9月。最初に手をつけたのが「企業経営理論」でした。
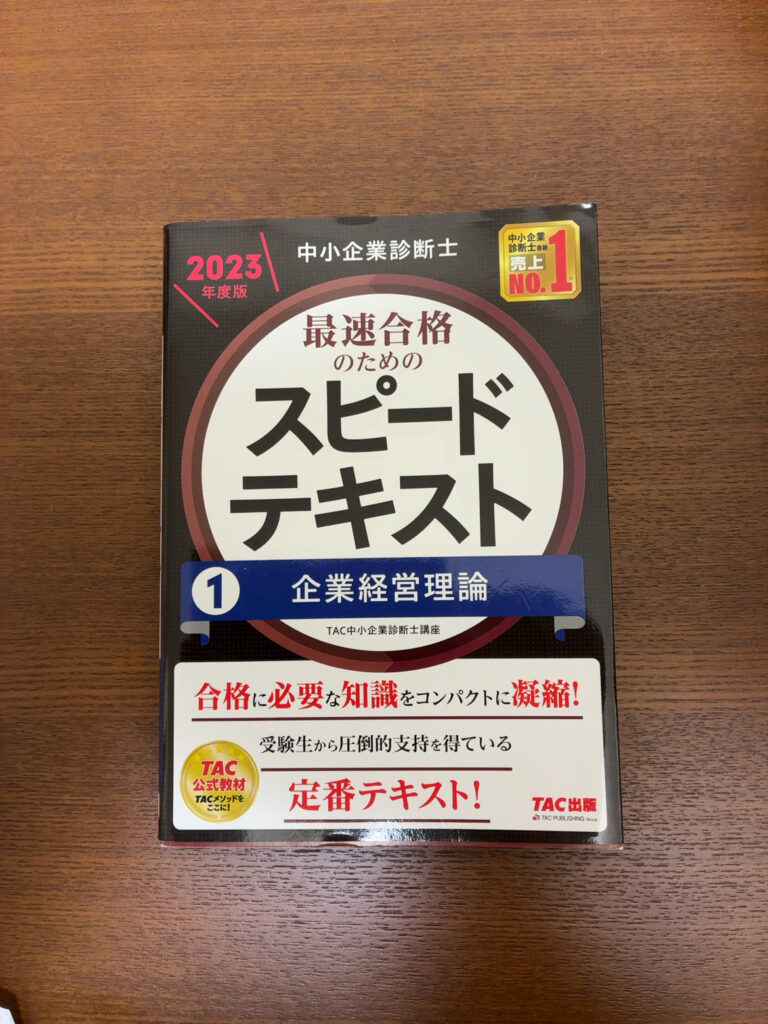
オススメされていたTACのスピードテキストを読み進めてみると、
- 経営戦略や組織論、人事制度など、実務とリンクする内容が多く
- 丸暗記ではなく、理解しながら覚えられる構成で
- 勉強そのものが楽しいと感じられた
という印象が強く、初学者の自分にも非常に親しみやすい科目でした。
一度後回しにして財務・会計へシフト
「これはいけそうだ」と思ったからこそ、逆に「後回しでも間に合う」と判断。そこで、次に手をつけたのが「財務・会計」です。2024年10月から12月までの3ヶ月間、この科目に集中しました。
ところが、想像以上に苦戦しました。
- 簿記の知識がなかったため、仕訳のルールにまずつまずく
- 計算問題は難易度が高く、勉強に時間がかかる
- 解法パターンを覚えるだけでは対応しきれず、点数に結びつかない
努力はしたものの、「このペースだと全7科目の合格は正直厳しい」というのが率直な感想でした。
勉強計画を見直し、3科目に絞る決断
年末の段階で、2025年8月の試験までに全科目の仕上げは不可能と判断。そこで、方針を変更し「まずは3科目で合格実績を作る」という1.5年計画に切り替えました。
絞り込んだのは以下の3科目です。
- 経営法務
- 中小企業経営・政策
- 経済学・経済政策
加えて、経営情報システムについては応用情報技術者試験に合格済みだったため、免除申請を行いました。このおかげで、学習負担をさらに軽減できたのは大きかったです。
一方で、「企業経営理論」は本来なら重要な科目です。というのも、二次試験の事例I(組織・人事)や事例II(マーケティング)と深く関連しているためです。
しかし逆に言えば、二次試験の準備を本格化させるタイミングで改めて企業経営理論を復習する方が、一次・二次の内容をリンクさせて理解できると判断。そのため、今回はあえて翌年に回す方針としました。
3科目の手応えがよく、「もう1科目いけるかも」となる
2025年2〜3月に3科目の勉強を集中して行った結果、思った以上に順調に仕上がってきました。ここで初めて「もしかすると、もう1科目追加してもいけるかもしれない」と思い始めます。
とはいえ無理は禁物。企業経営理論に対しては、
「受けて受かったらラッキー。落ちても別にいい」
という軽いスタンスで4月から再スタートを切りました。
4月〜5月:テキストと問題演習をゆるく復習
実際に行ったのは以下の通りです。
- スピードテキストをざっと2周
- スピード問題集を2周、感覚を確かめるように解く
- 過去問完全マスターはランクA問題だけを2周、ざっと読んだ程度
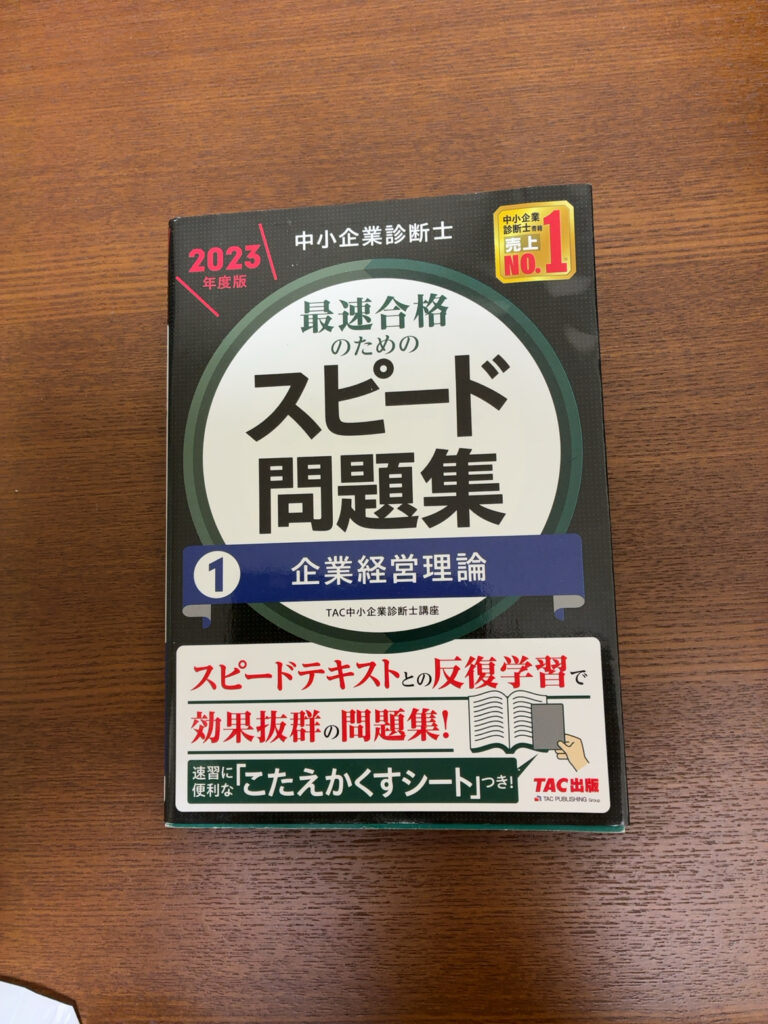
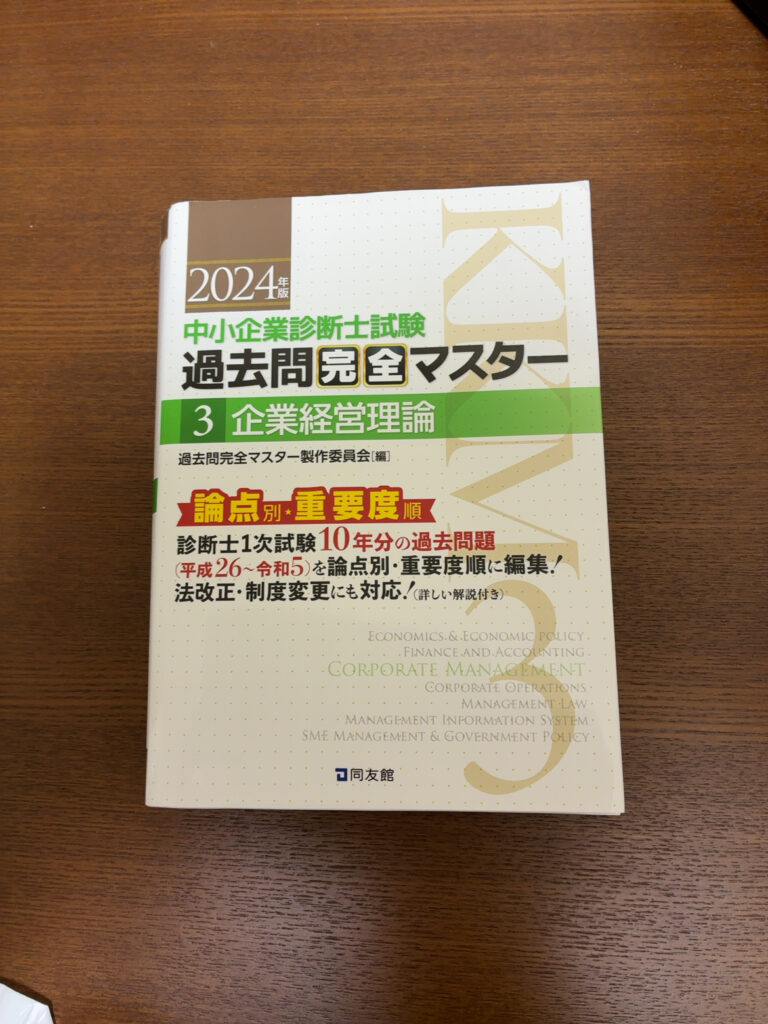
そして、5月にはTACのステップアップ模試を受験。結果は59点で、合格ラインの60点には届かないものの「これなら受験しても損はない」と判断できる内容でした。
その後、3科目に集中するため、企業経営理論の勉強はストップ。試験当日まで、たまにテキストをさらっとみるくらいで、ほとんど勉強したとは言えないくらいでした。
そして迎えた本番当日。前日すら勉強していませんでしたが、試験直前に40分の休憩時間があったので、この時間を活用して、事前に買っておいた「まとめシート流」のテキストをざっと読み返しました。
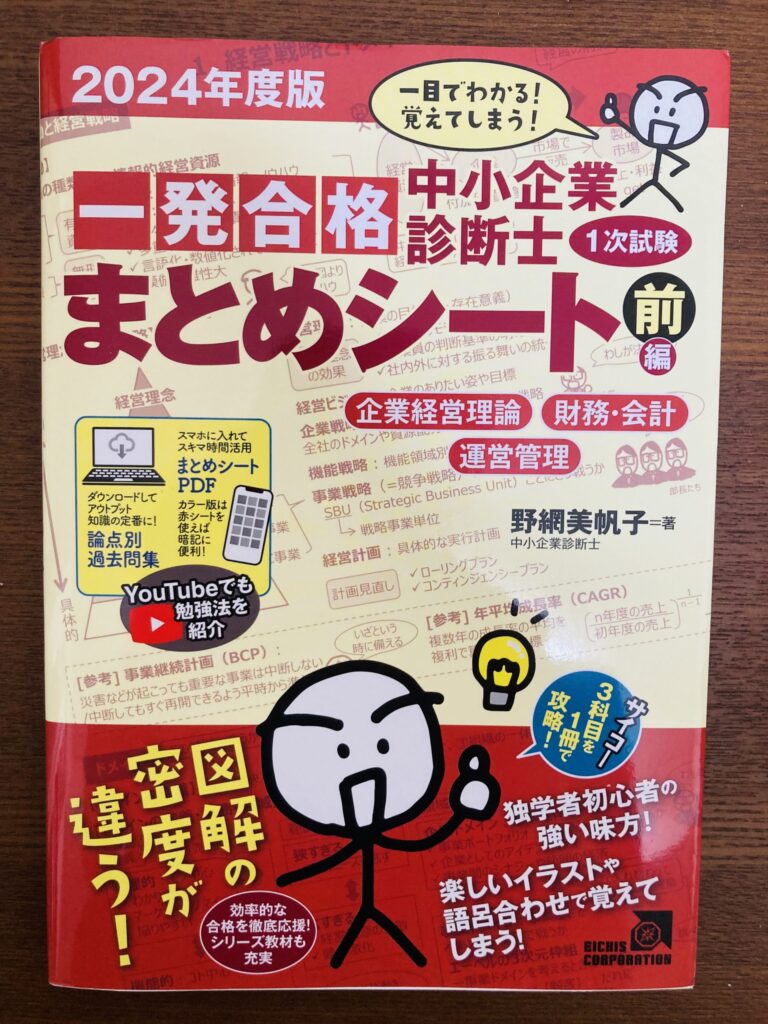
暗記というよりは、
- あ、こんな論点あったな
- この用語、前にも出てきたな
といった軽い確認で、感覚を研ぎ澄ます時間でした。
実際の試験は“国語力”でも解けた
本番の問題は、「これは明らかにおかしい」とわかる選択肢が多く、読解力でも対応できる内容でした。
- 表現に違和感のある選択肢
- 文脈とズレている記述
- 常識的に考えて不自然な文章
こうした選択肢を消去することで、知識の記憶が曖昧でも正答にたどり着ける問題が多く、思った以上に手応えがありました。
本当の実力以上の点を取るには?りほさんの記事がヒントに
私自身、企業経営理論は“ラッキー枠”のつもりで受けたにも関わらず、想定以上の点数を取ることができました。その理由を振り返ってみると、「読解力」や「違和感を察知する力」が非常に効いたと感じています。
このように、知識の量以上に点数に直結する“読み解きの力”については、人気YouTuberの診断士ラボとして活躍もされている、りほさんが書かれた以下の記事にて言語化されています。
企業経営理論で95点取った私による、2択3択を正解に導く解き方【神通力講座】
この記事では、
- 確実に間違いな選択肢に×を付ける力
- なんとなくこっちが正解っぽいを見つける力
この2つのスキルによって、実力以上の得点を出すことは可能であると述べられています。まさに、私自身が本番で使っていたのはこの感覚でした。
この記事はぜひ読んでおくと、試験合格の役にたつと思います!!
まとめ:企業経営理論は「軽めでも戦えた」
企業経営理論はボリュームがあり、「重たい科目」と思われがちです。
ですが、実際に受けてみると、
- 興味がわきやすく勉強しやすい
- 知識よりも読解力が問われる面もある
- ガッツリ暗記しなくても十分合格を狙える(勉強するに越したことはないですが)
という科目でした。
私のように「受けるつもりじゃなかったけど、受けてみたら受かった」というケースもあるので、「余裕があれば1科目追加してみるか」くらいのスタンスでも、全然アリだと思います。
この記事が、企業経営理論の勉強を進める方の励みになれば嬉しいです。
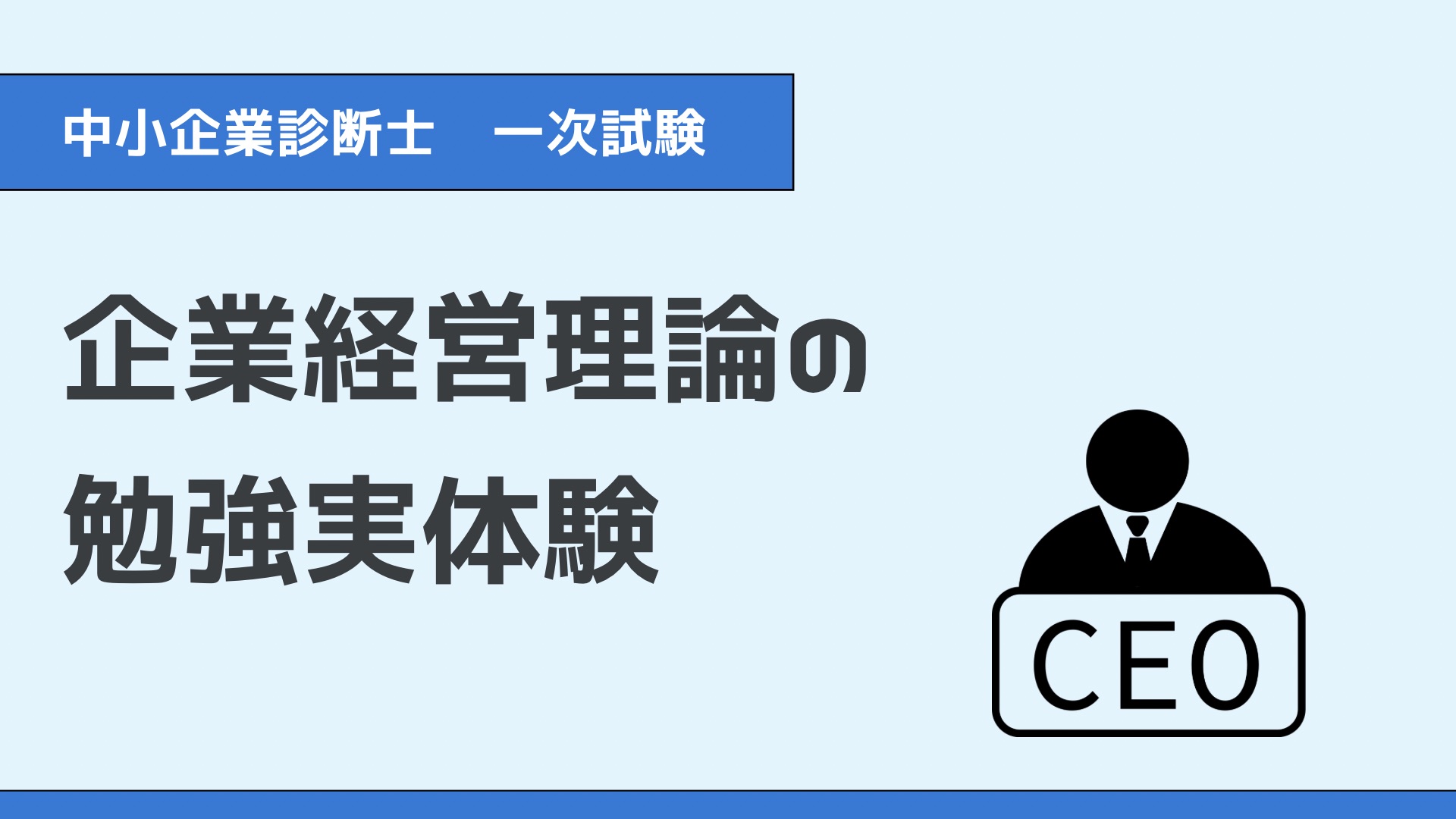

コメント