はじめに:「この勉強、本当に役に立つの?」と感じたあなたへ
中小企業診断士の勉強を始めると、ある瞬間ふと頭に浮かぶ疑問があります。
「これって、今の仕事や実生活に本当に役立つの?」
私はこの問いに何度も直面しました。しかし、勉強を続けていく中で、少しずつ確かな手応えを感じるようになってきたのです。
この記事では、私自身がインサイドセールスという実務の現場で感じた、診断士の学びが実務に活きた4つの効果をご紹介します。
1. 論理的に話す力が身につき、相手に伝わるコミュニケーションができるようになった
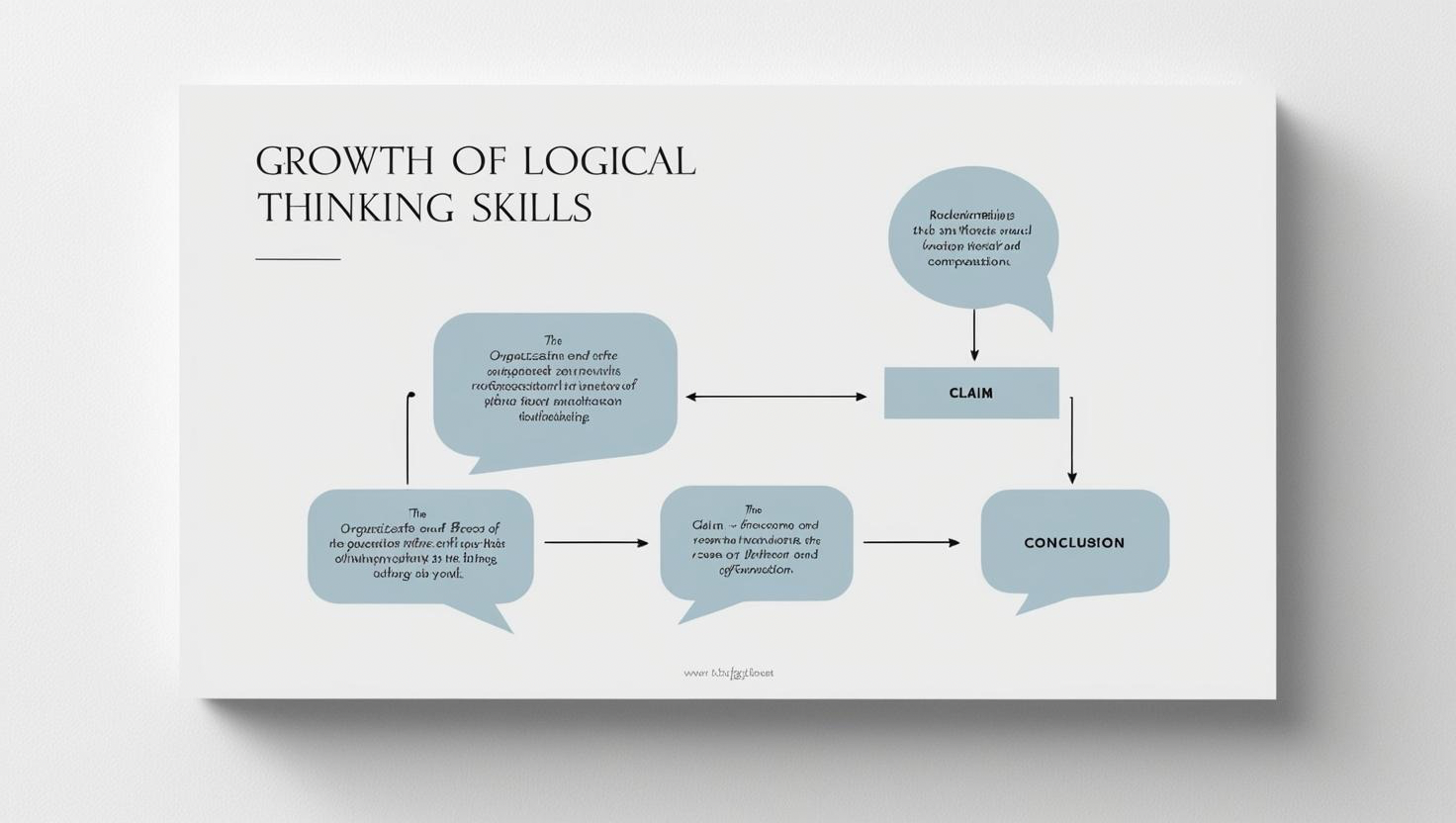
中小企業診断士の一次試験・二次試験では、知識だけでなく論理的思考力が強く求められます。
私もこの勉強を通して、「話し方」が大きく変わったと実感しています。
以前は話すときに順番がバラバラだったり、主観的な表現に頼りがちで分かりにくくなってしまうことがありました。
しかし、試験対策を通じて以下のようなスタイルが自然と身につきました。
- 結論から話す
- 根拠を筋道立てて示す
- 相手に伝わる順番で話す
今までは自分の自由時間をスマホやアニメ鑑賞に充てて、頭を全然使っていなかったのに対し、その時間を勉強で脳に負荷をかけるようになったので、ふと成長を実感することも多いです。
例えば、インサイドセールスではお客様との会話が1番大切な仕事で、難しい商品でも、相手が理解しやすい論理で簡潔に回答する力が求められます。その際に体感値ですが、ロジカルにより分かりやすく話せるようになってきた気がします。
また、社内で営業施策を上司に提案する際も、実際の数字等を踏まえて「この施策をやる理由」「なぜこのターゲットなのか」などを短時間でロジカルに伝える力が必要です。
今では「以前より話が分かりやすくなったね」と言われることも増え、仕事の信頼性も高まりました。
2. 財務・会計への理解が深まり、数字への親しみが増した
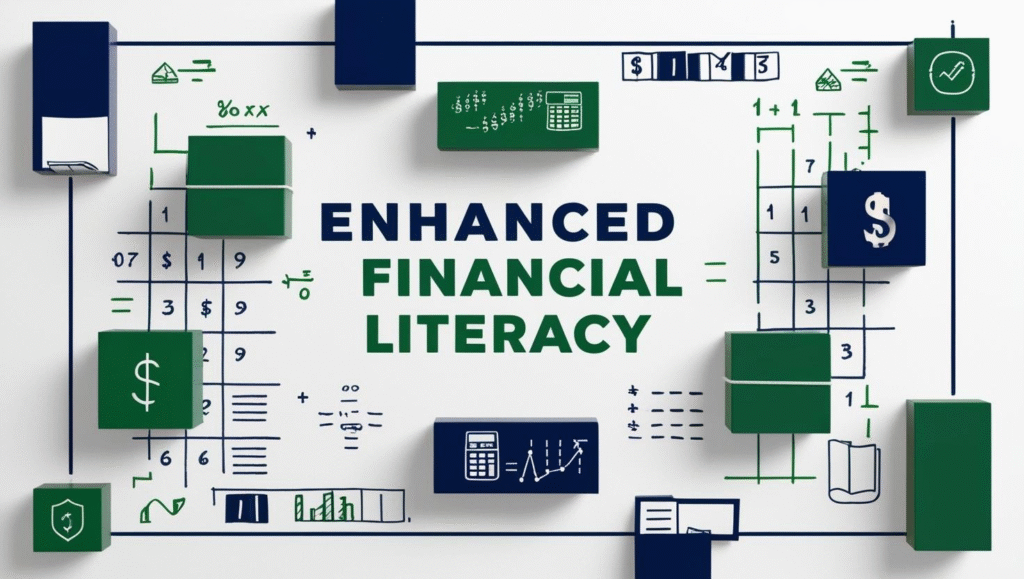
私は文系出身ですが、もともと数字に対する強い苦手意識はありませんでした。
それでも、診断士の勉強を通じて財務・会計の知識が体系的に頭に入り、理解がより深まったと感じています。
とくに印象的だったのは、財務諸表の構造が自然に頭に入ってくるようになったこと。
以前はぼんやりしていたBSやPLのつながりや意味が、「なるほど、こういうことか」とより高い解像度で腑に落ちるようになりました。
また、自分が関心を持っている企業の決算書を読むなど、その数字の背後にある経営の意図や動きに興味を持つようになりました。
勉強を通して、数字は単なる記号ではなく、企業活動そのものを映す「物語」だと感じるようになりました。
3. 日本経済新聞の内容がリアルに理解できるようになった

勉強を始める前、日本経済新聞は正直「難しいな…」という印象でした。
一面をざっと見て、気になる見出しだけ読む、という読み方しかできていませんでした。
しかし、診断士の勉強を進めていくうちに、経営、財務、政策、法律などに関する知識が増え、
新聞で使われている専門用語や制度、政策の背景がリアルに理解できるようになってきたのです。
たとえば、
- 中小企業支援策の文脈が理解できる
- 企業財務の話題が実感を持って読める
- 法改正や国策の意図を読めるようになった
単なる“情報”としてではなく、「今、自分のビジネスに何が起こっているか」を読み取る“洞察力”が身についたと感じています。
4. 忙しい中でも勉強を続けられた「習慣化の力」がついた

診断士の勉強をしていた当時、私はインサイドセールスの立ち上げを担当しながら、育児にも向き合っていました。
家事も多く担当しており、自由な時間はほとんどありませんでした。
そんな中でも、私は毎朝4時に起きて2時間勉強する習慣を続けました。
子どもが寝ている時間を使い、家族との時間を削らず、静かな朝を“自己投資の時間”にしました。
この習慣は、資格取得のためだけでなく、
- 時間の使い方の工夫
- 集中力の最大化
- 生活全体の計画力
といった、ビジネスパーソンとしての基礎力をも高めてくれたと感じています。
まとめ:診断士の学びは“今”にも“将来”にも効く
中小企業診断士の勉強は、ただの資格試験ではありません。
私自身が実感した変化は、次のようなものでした。
- 論理的に伝える力が仕事で活きた
- 財務や会計への理解が深まり、数字への親しみが増した
- 新聞やニュースの内容が現実とつながって見えるようになった
- 忙しくても学び続ける「習慣化の力」がついた
以前は「勉強しても意味あるのかな?」と迷うこともありましたが、今はこう考えています。
「資格だけでなく、その学ぶプロセス自体にも意味がある」
これからも勉強頑張っていきます!
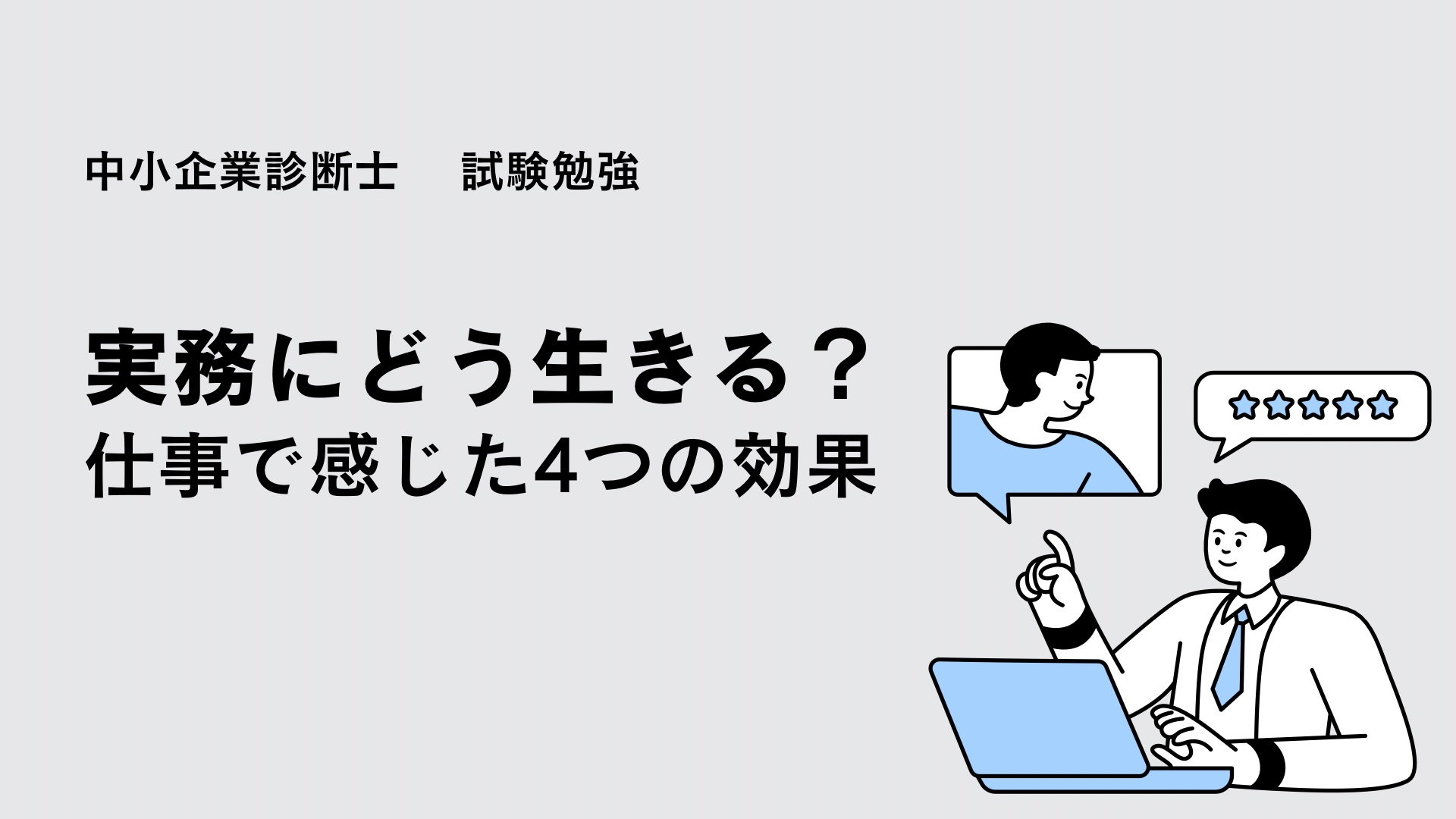
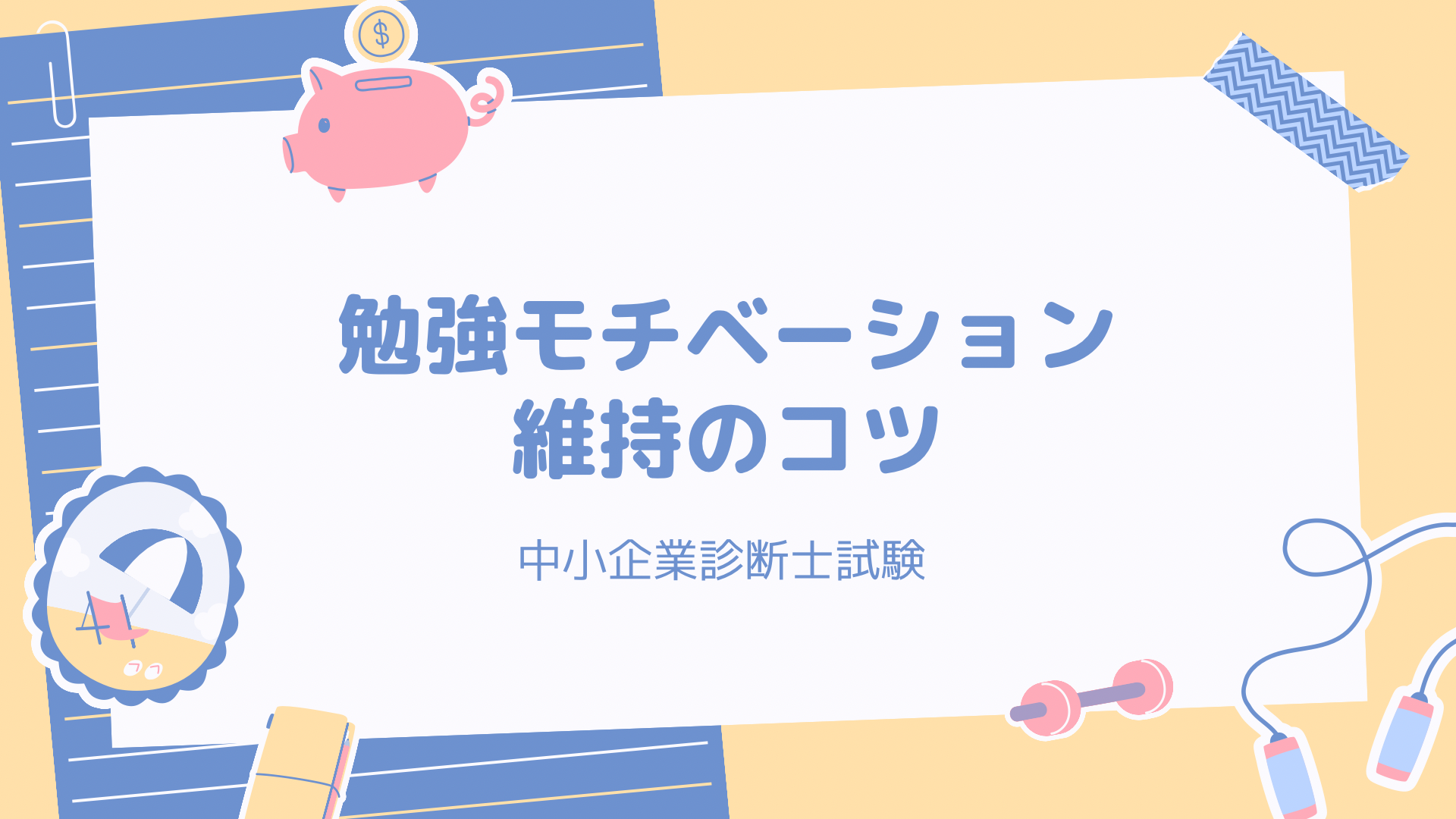
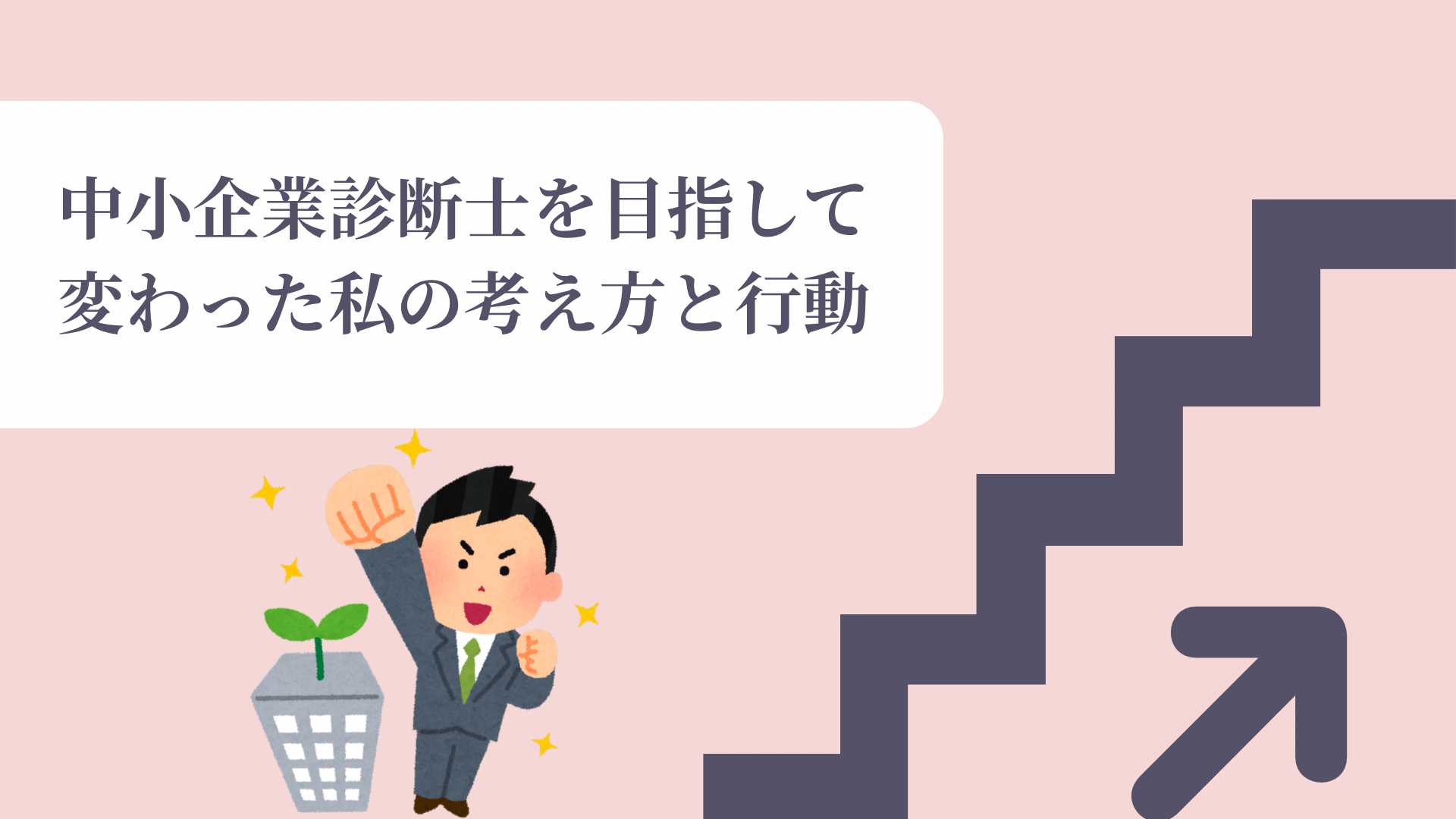
コメント