中小企業診断士一次試験|【財務・会計】簿記ゼロでテキスト読んで仕訳が理解できなかった私が、まさかの60点で科目合格した話
中小企業診断士の一次試験の中で、「財務・会計」は最も鬼門の科目だと多くの受験者が口をそろえます。
そして実際に、私にとってこの科目はまさに“異世界”のようなものでした。
なぜなら、私は簿記の知識がほぼゼロの状態で試験に臨み、仕訳だけが全く理解できないまま受験したからです。
そんな状態で受けてどうなったか。
なんと、60点で科目合格してしまいました。
今回は、そのリアルな体験をもとに、私がやったこと、やらなかったこと、今だから言えることを包み隠さずまとめます。
スピードテキスト2周で「仕訳以外」は理解できた
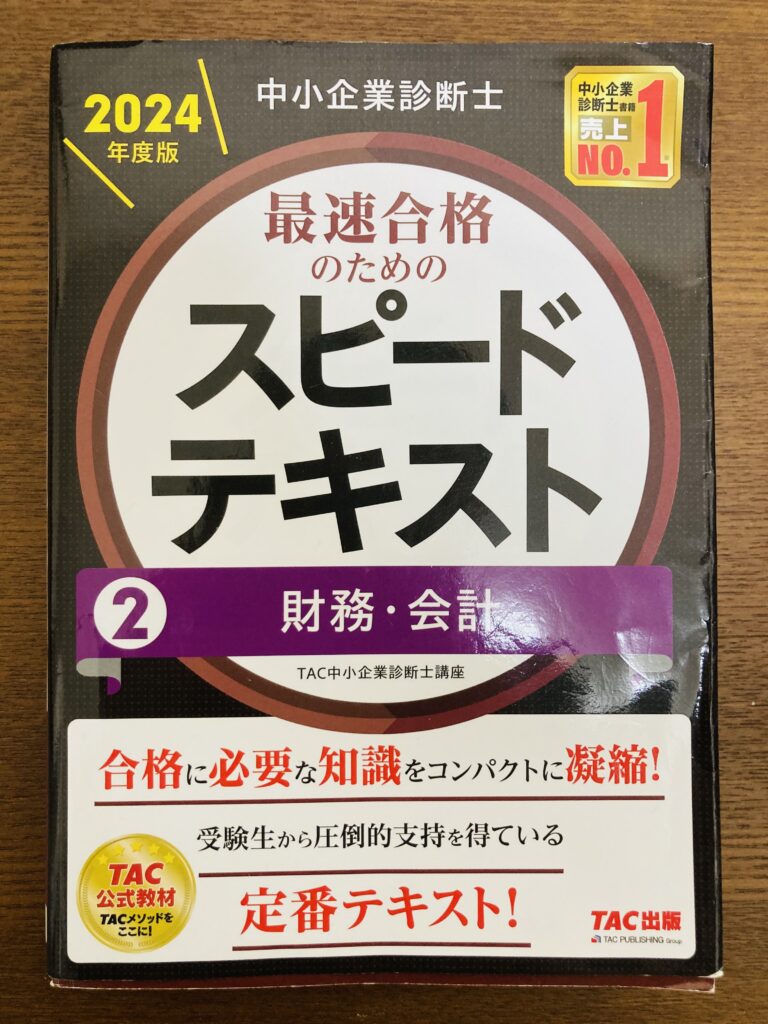
勉強を始めた当初、私はTAC出版の「スピードテキスト(スピテキ)」を使って、全体を2周読み込みました。
この時点で、CVP分析、NPV、DCF法、損益分岐点分析などの計算問題や理論論点については、割と理解できていました。
「これなら、繰り返して練習すればいけるかも」という感触もありました。
ただ一つ、「仕訳」だけはまるで呪文だった
ところが、仕訳の単元だけは、どうしても理解できませんでした。
「現金が借方? 売上が貸方? なぜ???」
スピテキに書かれていることは何となく読めるのに、勘定科目がどう動くのか、なぜこうなるのかが全くつかめない。
しかも当時は、“自分が何を理解できていないのかすら分からない”という状態。
そんな中でもとりあえずアウトプットの勉強をしようとスピード問題集にも手を付け、これも2周はしました。
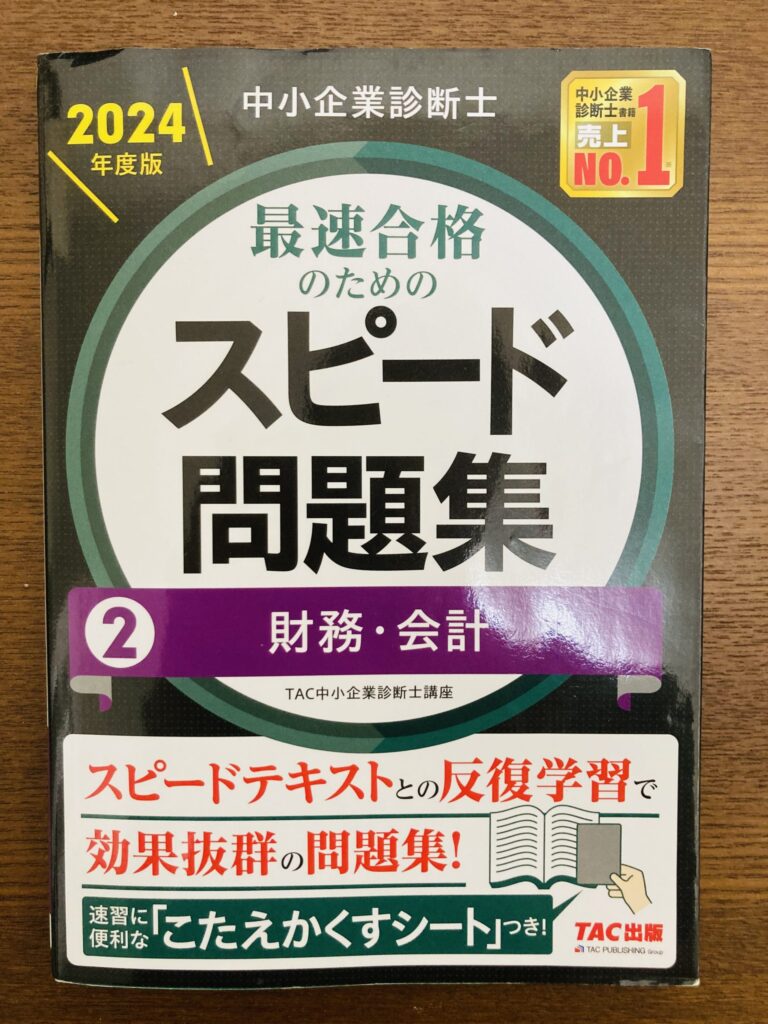
とはいえ問題も全然解けず、特に仕訳は解答を読んでも理解できない。とにかく混乱していて、仕訳の問題だけは「無理だ」と早々に諦めました。
「今年は財務・会計は無理」そう判断して完全に手を引いた
この時点で、私はこう判断しました。
「仕訳が理解できないなら、いったん撤退しよう」
「簿記からやり直して、来年受ければいい」
2024年1月を最後に、財務・会計の勉強は完全にストップ。
以降は模試も受けず、スピテキも開かず、完全に「放置」しました。
試験当日、まとめシート流を会場に持って行った
そんな私が、試験当日に唯一やった“財務会計っぽいこと”が一つだけあります。
それは、「一発合格まとめシート」を会場に持っていって、40分の休憩時間にざっと眺めたことです。
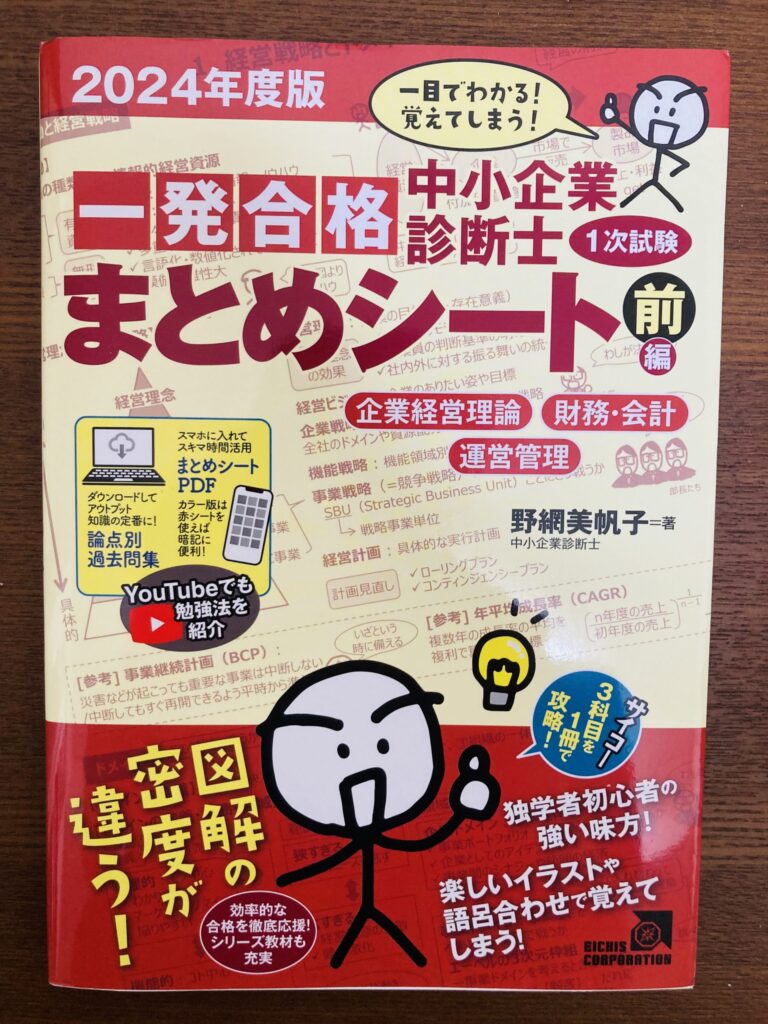
ただ当日、要点だけ見れればと思い持って行きました。
細かい理解や暗記はできませんでしたが、なんとなく「財務会計ってこういう分野だったよな…」という空気感を再確認できた気がします。
それが、後々意外な形で効いてきました。
実はこの40分間だけ「とりあえず本番は経験しておこう」「受験料ももったいないし」という理由で、勉強したのです。
他の科目を詰め込んでもどうせ忘れると思い、来年のための“場慣れ”くらいのつもりで。
そして本番:運だけで乗り切った60点
仕訳の問題は手も足も出ず、完全にスルー。
計算問題は、分かるものだけ解きました。
そして、残りの問題については、以下のような“最後のあがき”でマークを塗りつぶしました。
- 選択肢を眺めて、明らかにおかしそうなものを切る
- 数字の大小や常識的におかしそうな選択肢を外す
- 4択の中から“なんとなくっぽい”ものを選ぶ
つまり、「運」です。
知識で解けたのはせいぜい2〜3割程度。
あとは完全に勘とマーク運。
それでも、なぜか合計60点で合格してしまったのです。
正直、自己採点の結果見たときは目を疑いました。
一次試験後に簿記を学んで気づいた「致命的な欠落」
一次試験が終わった後、私は改めて簿記3級から勉強を始め、最終的には簿記2級にも合格しました。
そこで初めて気づいたのです。
「あの時の自分は、勘定科目の意味すら分かってなかった」
「そりゃ仕訳が理解できないわけだ」
借方・貸方の考え方、資産・負債・収益・費用の分類、仕訳のルール…
簿記3級で扱うような“超基本”が完全に抜けていたのです。
当時の私は、それに気づく余裕すらなく、「スピテキに書いてあるのになぜ理解できないのか?」と頭を抱えるばかりでした。
スピテキで仕訳が理解できなければ、簿記3級から始めるのが近道
今、もしあなたが私と同じように、
- 「スピテキは読めるけど、仕訳だけがまったく理解できない」
- 「勘定科目ってなんで動くの?ってずっと思ってる」
という状態なら、簿記3級のテキストを一度読んでみることをおすすめします。
私は『スゴい!だけじゃない!!日商簿記3級』(マイナビ出版)を使って学びましたが、イラストが多く、感覚的に理解しやすかったです。二次試験の参考にと、同じシリーズで簿記2級も勉強し、無事2級も取れました。
仕訳の基本構造が見えてくると、財務会計の勉強もかなりスムーズになります。
まとめ:簿記ゼロのままでも、運が味方すれば合格することもある
60点で科目合格できたことは、正直に言って奇跡だったと思っています。
仕訳が分からず、勉強も途中でやめ、当日は「消去法+勘」で塗りつぶしただけ。
つまり、運。完全に運。
再現性はゼロに近いです。
でも、同じように苦しんでいる誰かにとっては、こう思えるかもしれません。
「諦めかけてたけど、もしかしたら自分も可能性はあるかも」
「仕訳が無理でも、他のところで点が取れればワンチャンあるかも」
もちろん、基本的にはしっかり勉強した方がいいです。
でも、スピテキで仕訳が理解できないなら、いったん簿記3級に戻るというのは、とても合理的な選択肢です。
あなたの勉強が、少しでも効率的で、そして報われるものになりますように。
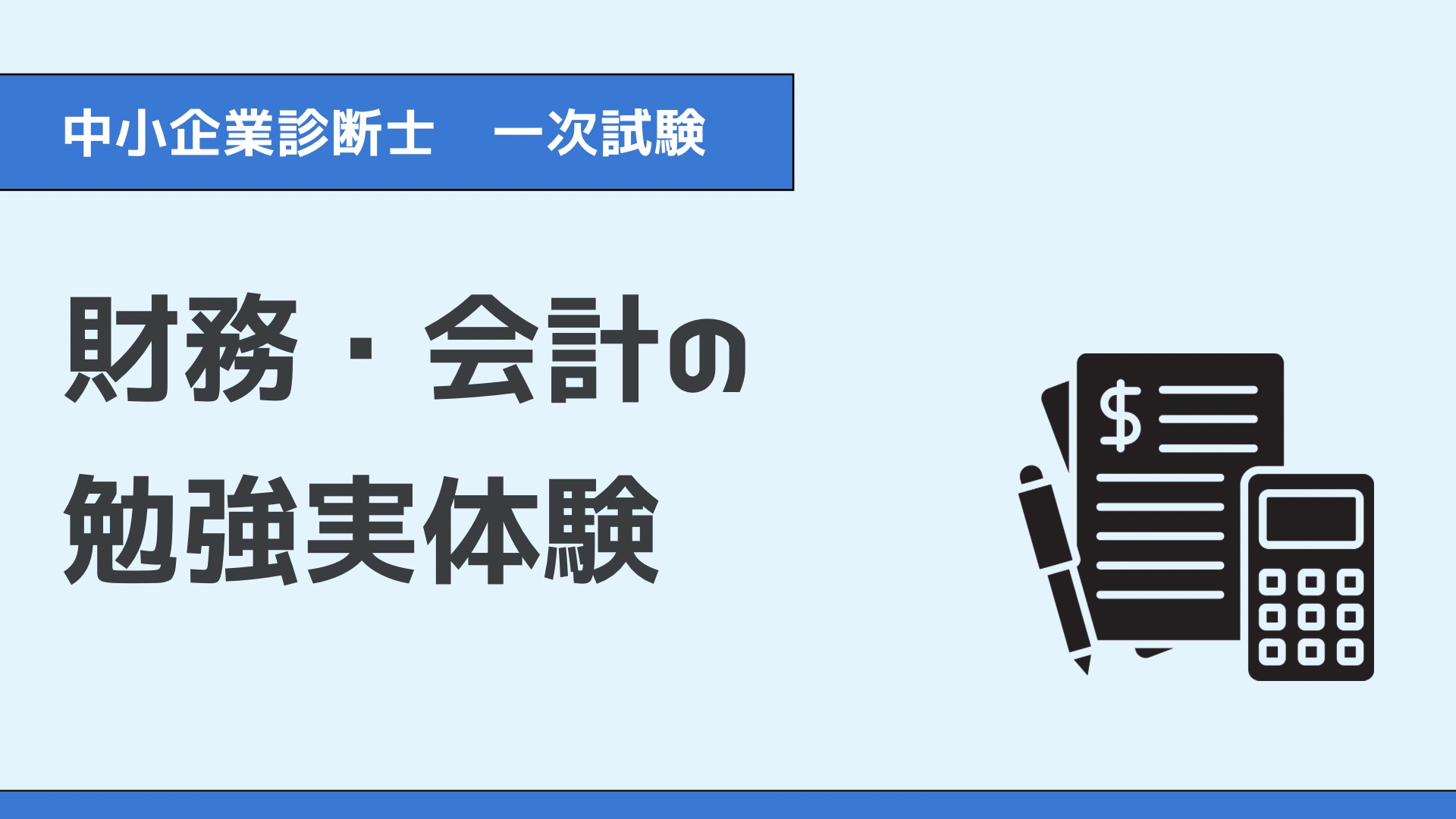


コメント