中小企業診断士一次試験|【経済学・経済政策】勉強実体験と使用テキスト
中小企業診断士の一次試験において、多くの受験生が構えてしまうのが「経済学・経済政策」です。マクロ経済、ミクロ経済、数式、グラフ……そう聞くだけで「自分には無理かも」と不安になる方も少なくないでしょう。
私は大学時代に経済学部に所属しており、教科書の内容には一度は触れていました。ただ、試験のように問題を解くのは実に10年ぶり。ほとんど初学者と同じレベルまで忘れしまっていました。
この記事では、そんな私が60点以上を安定して取れるようになるまでに実践した教材・勉強の進め方・考え方を、体験をもとに詳しくご紹介します。
経験者でもブランクあり、初学者とスタート地点はほぼ同じ
私は大学時代に経済学部出身で、マクロ経済学のゼミにも入っており、教科書で見た内容には一通り触れていました。しかし、卒業から10年が経ち、経済学の問題を解くのは本当に久しぶり。
最初に問題を解いたときの感覚としては、「あれ? 全然解けない……」という戸惑いが正直なところ。初めて経済学に触れる方と、実力差はほとんどない状態だったと思います。
ですから、「経済学を大学で勉強してこなかったから不利かもしれない」「経験者と差がついているかも」といった不安は、全く必要ありません。むしろ、診断士試験に出題される内容は一定の範囲に限られており、しっかり対策すれば誰でも得点源にできる科目です。
経済学は「理解+暗記」が成功の鍵
「経済学は理解が大事」とよく言われます。たしかにその通りで、IS-LMモデルやAD-AS分析、乗数理論など、ロジックを理解していないと少し捻られた問題に対応できません。
しかし、それだけに頼っていては試験対策としては非効率です。一から式を導出して考えていると時間が足りなくなるのも現実。そこで私は、以下のようなバランスを意識しました。
- 最初はしっかりと「なぜそうなるか」を理解する
- 試験直前期や演習時は、公式・手順をパターンとして暗記
また、軽視しがちなのが用語の暗記です。「GNPとGDPの違い」「クラウディングアウト」などの用語がそのまま問われることもありますし、定義を取り違えていると選択肢で迷ってしまいます。
ただし、用語問題の配点は全体の中ではそれほど高くありません。得点戦略としては、自分の勉強時間と相談しながら、重要用語を中心に取捨選択して覚えるのが現実的です。
使用教材と使い方:スピテキ→問題集→過去マス
私が使った教材は、すべて市販の王道3点セットです。
スピードテキスト(TAC出版)
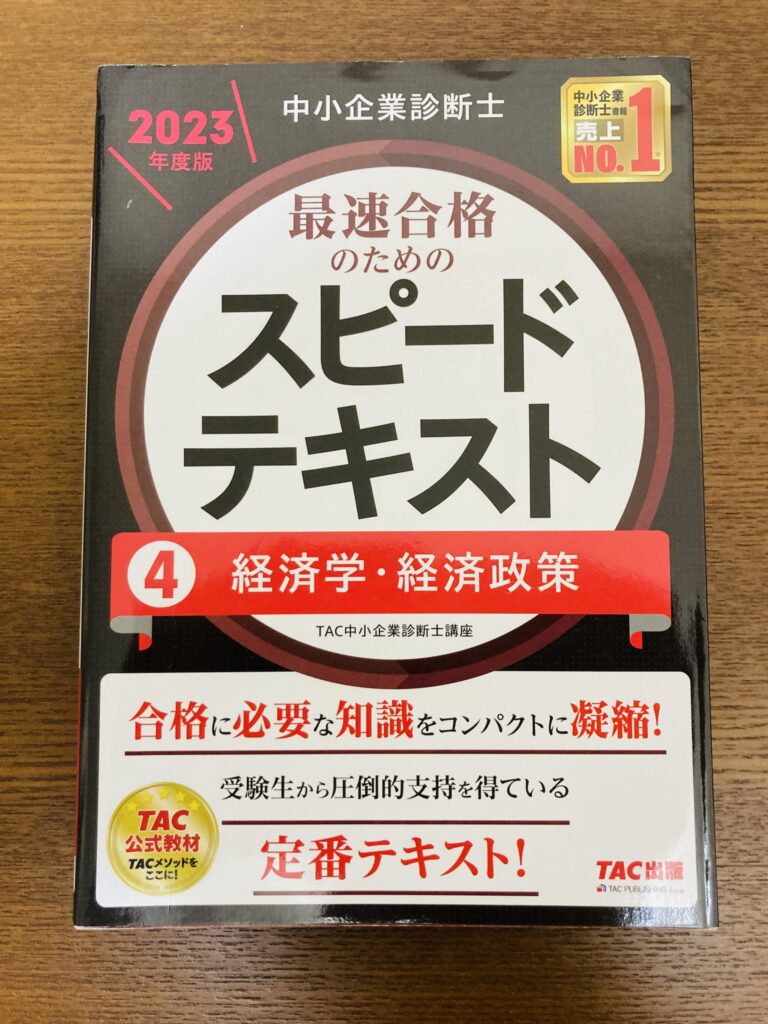
勉強開始したのが2023/10くらいなので、まだ受験年の2024版が無く、2023版です。
まずはスピードテキスト、通称「スピテキ」でインプットを行いました。一周目は流し読みではなく、しっかり理解することを意識して読み込みました。ここだけで2週間程度は使っています。
というのも、大学時代に「理解しないまま暗記で試験に臨んで痛い目を見た」経験があったからです。その反省から、「わかったつもり」で進まず、一つひとつ納得しながら読み進めるようにしました。
スピード問題集(TAC出版)
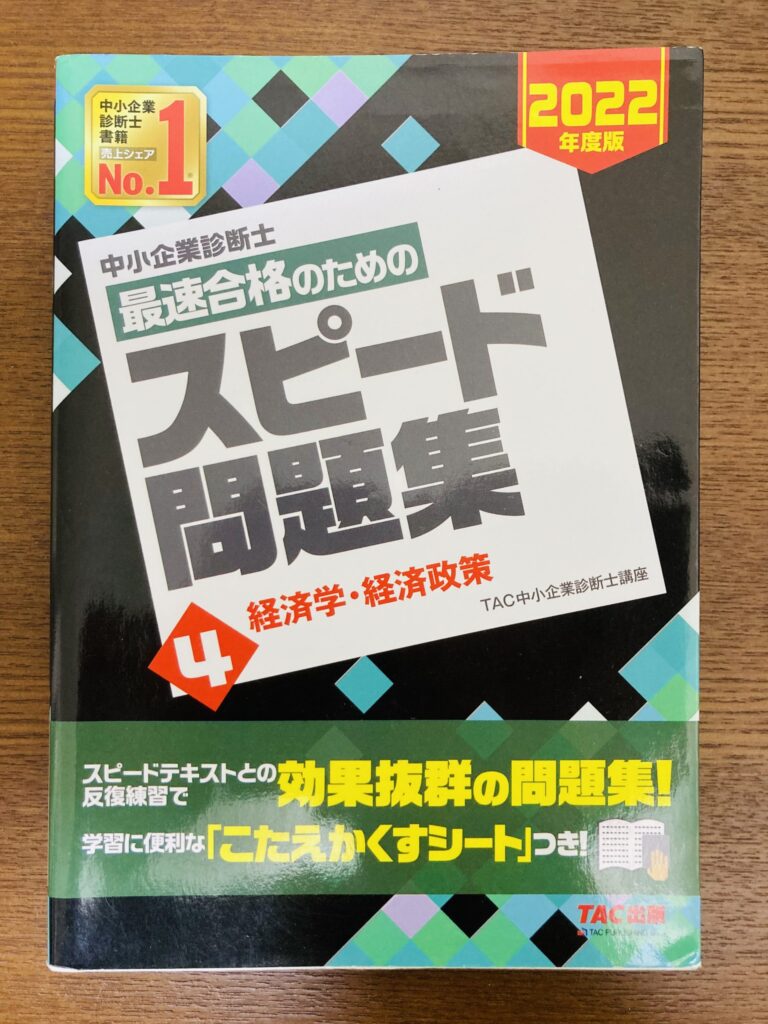
メルカリで安く前年度のを買いました。これで充分です。
スピテキを一周したあとは、スピード問題集に移行。2周程度回して、問題の出され方に慣れることを目的としました。問題集の段階では、「正解すること」よりも「なぜそうなるかを説明できること」を重視しました。
過去マス(同友館)
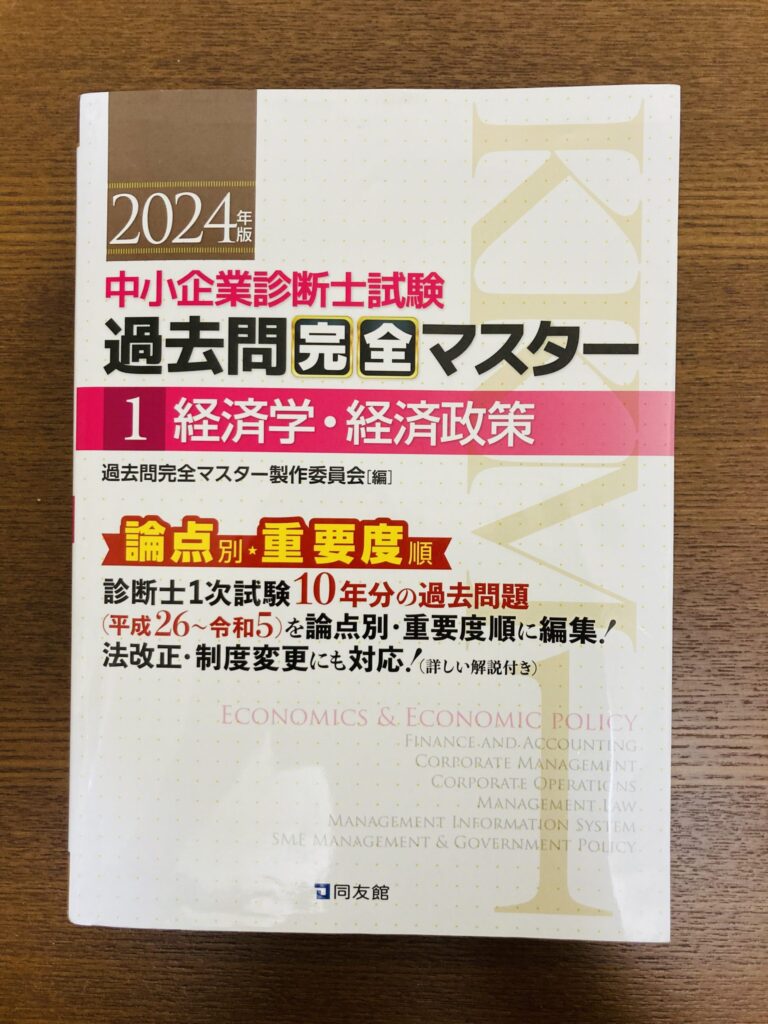
良さそうなのがなかったので、本屋で最新年度のを仕方なく買いました。
その後は、いよいよ本命の過去問演習へ。私は「過去マス」と呼ばれる過去問題集を使用し、最終的に5周以上繰り返しました。
目標は、「問題文を読んだ瞬間に、何を問われていて、どう解けばいいかがわかる」状態にすること。やはり一次試験では過去問が超重要です。試験本番でも、過去マスで見たのとほぼ同じ構成の問題も沢山出てきて、「これは解ける」と自信を持って取り組めました。
「わからない」は動画で補強
テキストを読んでいて「どうしてもピンとこない」と感じることは当然あります。そういうときは、YouTubeなどの解説動画を使って補強していました。
「IS-LMモデル」「乗数理論」「財政政策の効果」などのテーマは、図解と音声で説明してくれる動画のほうが圧倒的にわかりやすいです。
私の場合は、「教科書を読んでも何故こうなるのかピンとこない箇所だけ動画で補強する」という使い方をしていました。これだけでも、学習効率がかなり上がります。
経済学は出題パターンを押さえれば得点源になる
中小企業診断士試験の経済学は、決してランダムに出題されているわけではありません。出題パターンはある程度決まっているため、特定の論点を重点的に対策することで、効率よく得点できます。
たとえば:
- マクロ経済:IS-LMモデル、AD-AS分析、財政政策、乗数効果
- ミクロ経済:限界費用と平均費用、価格弾力性、余剰分析
これらは毎年のように出題されるなど、求められるは変わりません。逆に、難問・奇問に出くわしたときは、深追いせずに飛ばす勇気も必要です。
まとめ|過去マスをしっかり勉強し、慣れれば誰でも戦える科目
中小企業診断士の一次試験において、「経済学・経済政策」は確かにとっつきにくい科目です。ただし、「中小企業経営・政策」のように、毎年のように制度変更に伴う試験内容が変化が起こる、と言ったものではなく、理論が数年で変わる事もないので、試験範囲は毎年ほとんど変わりません。
私は大学時代に経済学を学んだとはいえ、10年のブランクがあり、最初は初学者と大差ない状態でした。それでも、教材をやり込み、パターンを覚え、足りない部分は動画で補強するという形で、60点以上を安定して取れる実力をつけることができました。
経済学が未経験の方でも、焦る必要はありません。「わかるまでやる」「見たことある問題にする」ことを意識すれば、誰でも得点源にできます。
これから受験される方にとって、この記事が少しでも参考になれば幸いです。
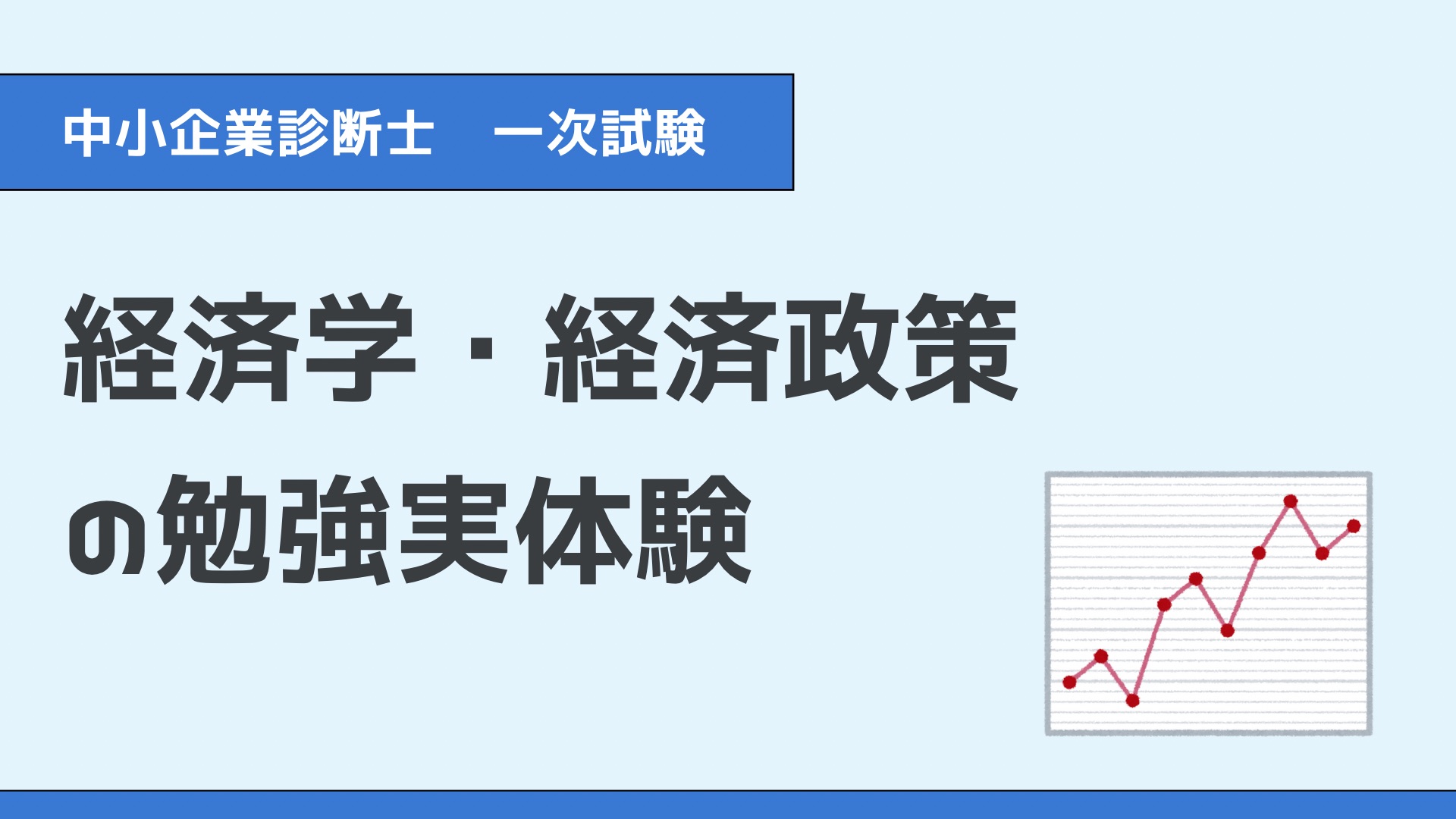


コメント