中小企業診断士の二次試験では、「事例Ⅰ〜Ⅳ」と呼ばれる記述式の4科目に取り組みます。中でも事例Ⅰ〜Ⅲは、企業の組織・マーケティング・生産などがテーマとなっており、正解が一つに定まらないという難しさがあります。
私は現在、二次試験に向けて勉強を進めている段階です。一次試験は独学で合格しましたが、二次試験に取り組み始めてすぐに、その違いの大きさに戸惑いました。
- 与件文を読んでも、何が言いたいのかつかめない
- 書いた解答が模範解答と全く違う
- 採点基準が見えず、正解に近づいている感覚が持てない
この記事では、勉強中の私が感じている事例Ⅰ〜Ⅲの特徴や、つまずいたポイント、よさそうと感じている勉強の進め方をまとめます。まだ明確な答えやコツが見えているわけではありませんが、同じように悩みながら勉強している方のヒントになれば嬉しいです。
◆ 二次試験ってどんな試験?
- 実施:年1回(10月下旬)
- 形式:筆記式(マークシートなし)
- 科目構成:
・事例Ⅰ:組織・人事
・事例Ⅱ:マーケティング・流通
・事例Ⅲ:生産・技術
・事例Ⅳ:財務・会計 - 合格条件:総得点60点以上かつ40点未満の科目がないこと
事例Ⅰ〜Ⅲはどれも「与件文を読み取り、それを根拠に記述する」ことが求められます。ただし、その“読み取り方”や“書き方”の正解が見えにくいため、勉強初期は特に戸惑うことが多いです。
◆ 事例Ⅰ:組織・人事の事例
●テーマ
- 組織構造の見直し
- モチベーション施策
- 人事制度の改善 など
●戸惑った点
最初に取り組んだ事例Ⅰでは、「設問の意味が分からない」「どう答えるのが正解なのか見えない」と感じる場面が多くありました。
設問に「助言せよ」「要因を説明せよ」といった表現が多く出てきますが、それに対してどう構造的に答えればいいのかが分からず、与件文をどう活かせばよいのかも見えていませんでした。
●今意識していること
「組織論」や「モチベーション理論」などの知識と、与件文の内容をつなげる意識を持つようにしています。
また、最近はあえて与件文を読まずに設問文だけを見て、自分なりの回答を考えるトレーニングも取り入れています。
これは、「そもそもどんな視点・観点で答えるべき設問なのか」を見極めたり、自分の知識・フレームの引き出しを点検したりするためです。本番では与件に忠実な回答が必要ですが、設問の形式や論点パターンを把握することは、読むべき与件のポイントを探す助けにもなります。
◆ 事例Ⅱ:マーケティング・流通の事例
●テーマ
- 売上拡大
- 新規顧客の獲得
- 商圏分析や販促施策の提案 など
●印象とつまずき
事例Ⅱは、他の事例と同様に現実味のある中小企業が題材となっていますが、与件文の中に答えのヒントが比較的明確に書かれている印象を受けました。
そのため、「設問に対して、与件のどの情報を活用すべきか」が他の事例よりも見えやすく、初心者でも取り組みやすいと感じています(※実際に合格点を取れているわけではありませんが…)。
●進め方
SWOTや4P(製品・価格・販路・販促)などの基本フレームを使って、与件から「強み」「機会」を抽出し、それに合った具体的な施策を考えるようにしています。
この事例でも、与件なしで設問だけを読んで施策を考えてみる練習を挟むことで、「こういう問いにはこう答える」という頭の型が少しずつ身についてきました。その上で、実際の与件を読むと「この情報はここに活かせるな」と結びつけやすくなった実感があります。
◆ 事例Ⅲ:生産・技術の事例
●テーマ
- 工場の生産効率化
- 業務の標準化
- 品質・納期の改善 など
●自分の課題感
私は一次試験の際にこの分野をあまり深く勉強しないまま合格してしまったこともあり、知識が不十分なまま過去問に挑んで苦戦しました。
与件文の読み取り自体はできているつもりでも、使える用語や典型的な改善パターンが頭に入っておらず、解答を書く際に「書けそうで書けない」状態が続いています。
●現在取り組んでいること
まずは、QCD(品質・コスト・納期)の観点で課題と対策を整理しながら、知識の補完を優先しています。
そのうえで、こちらも設問文だけを抜き出して「この課題ならどう改善できるか」を考えてみる練習をしています。
この練習は、知識の引き出しを点検するのに効果的で、アウトプットの整理にもなると感じています。
◆ 共通して意識していること
すべての事例に共通して感じているのは、「与件文に沿って、そこに書かれた情報をどう活かすか」が最も重要だということです。
その一方で、あえて与件文を使わない練習を取り入れることで、設問の型や問い方に慣れたり、回答パターンを意識的にストックすることにもつながると感じています。
インプットとアウトプットの両面を行き来しながら、少しずつ「書ける状態」に近づけていけたらと思っています。
◆ まとめ:まだ試行錯誤の途中ですが、一緒に進みましょう
この記事では、二次試験の勉強を始めたばかりの私が、事例Ⅰ〜Ⅲに対して感じた特徴やつまずき、そして今試している勉強方法についてまとめました。
まだ「こうすれば点が取れる!」という確信があるわけではなく、むしろ模索中のことばかりです。ですが、少しずつ知識と視点を補いながら、事例に向き合っていく過程こそが、合格に近づくための土台になると信じています。
これからも、過去問演習や気づきを記事にしていく予定です。同じように悩んでいる方にとって、「自分だけじゃない」と思えるような存在になれれば嬉しいです。
一緒に一歩ずつ、進んでいきましょう。
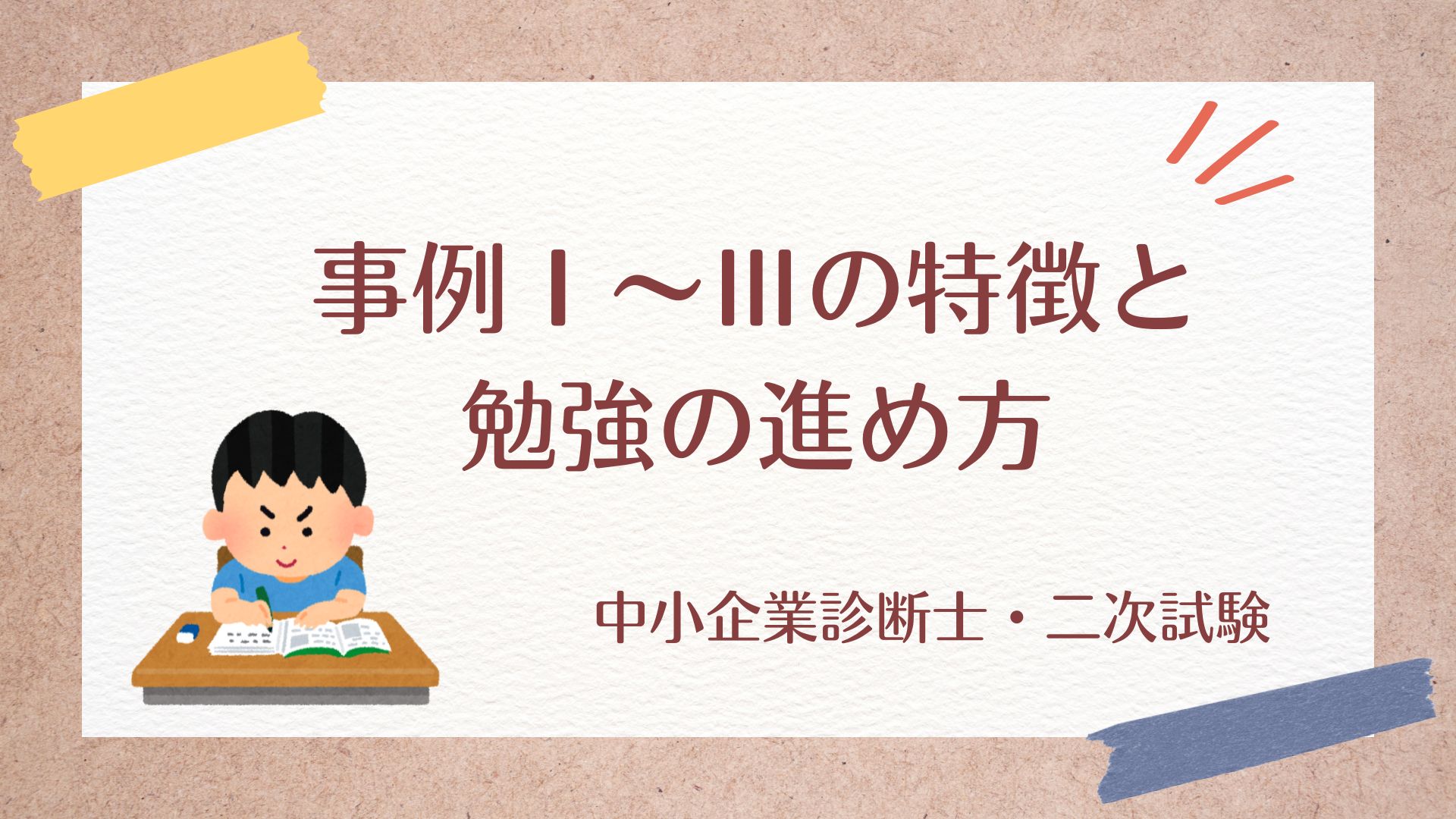
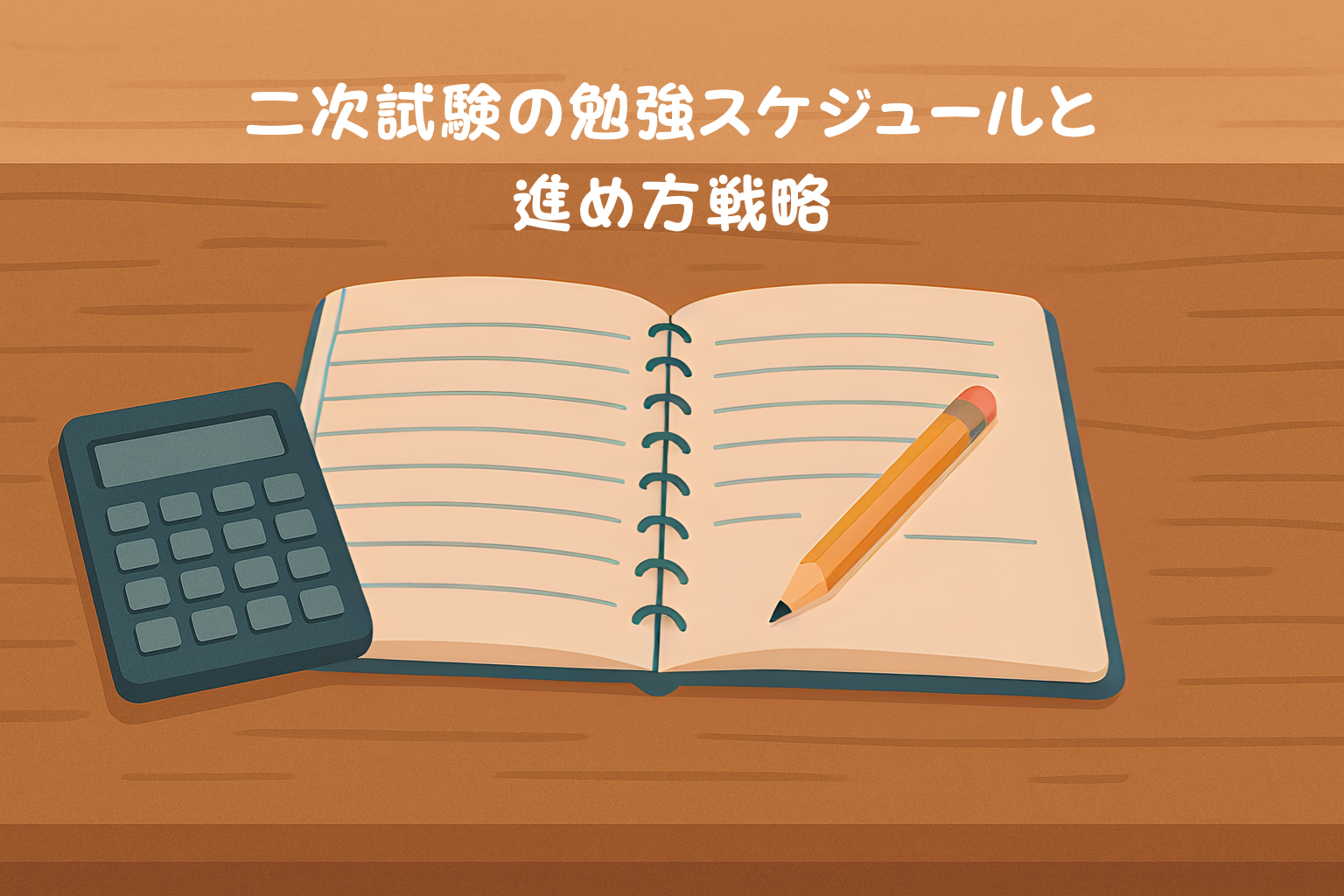

コメント